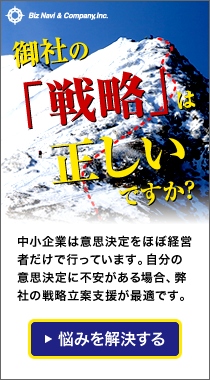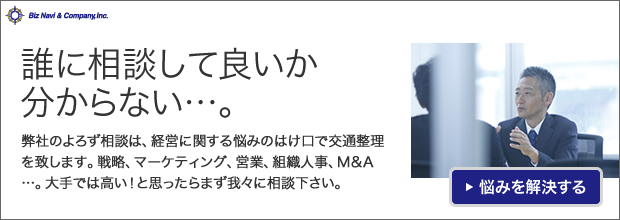早嶋です。
成熟事業でキャッシュを得る企業の多くは新規事業開発に課題を持つ。一方で、新規事業開発を積極的に進めている企業は、事業開発の手法にオープンイノベーションを活用している。NEDOによるとオープンイノベーションは、”組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである”と語られる。
新規事業を開発する手段としては、完全に時前で行う方法と、外部リソースを活用する方法がある。オープンイノベーションは双方を融合した手法だ。企業が事業開発を自前で行う場合、いわゆるゼロイチのフェーズで、オープンイノベーションといいながら従来の思考、時間軸、ネットワーク、業界で議論をしがちだ。従い、セレンディピティ的な事象が起きにくく閉塞感を伴うことが多い。そもそも従来の延長で議論をして新規事業が開発できていれば、今苦しんでいないはずなのだ。
そこで本稿でも度々議論しているが、ゼロイチの次は何故かM&Aに希望を持つ。新規事業を買うことで解決しようと考えるのだ。が、繰り返し何度も言うようにM&Aは万能ではなく、簡単では無い。
そこで、いよいよオープンイノベーションを実施することになるが、どうもベンチャーだ!ということでベンチャーキャピタルと関係を強めて情報を集めようとする。この取組自体は間違っていない。ベンチャーキャピタルは様々な得意分野があり、その得意分野に関する情報と周辺の話は確実に集まってくるからだ。
しかし、ベンチャーキャピタル(VC)にお金を費やしても、なかなかオープンイノベーションでの自社事業展開に結びつかない。基本的なベンチャーキャピタルは、複数の資本家からLP投資を受け、その金額から運営費をまかないながら特定分野に投資をする。ベンチャー企業に出資をするのはVCで、LPとVCは通常10年の運用契約を結ぶ。
企業がLP投資をしてVCを通じてベンチャー企業に出資をすることは可能だが、基本的に複数のLPの話を聞いて合意をとって投資とはいかない。VCの目的は自ずと財務リターンを最大化することになる。
では、オープンイノベーションをどのように進めるのがよいのかだ。基本的には、自社や事業の現在から将来にわたる課題を整理しながら、その課題の解決ができるパートナーを都度さがしながら、提携しながら取り組むことを提案し続けることだ。
通常、ベンチャー企業はプロダクトを有することが多い。イノベーティブな技術や視点が異なるアプローチで商品開発を行っている。一方で、成熟した企業は組織を活用した営業力やこれまで培ってきた特定エリアのネットワークを有す。また製品の品質を向上したり、小規模生産を大規模生産に展開するなどを得意とする。そのため将来の課題を保管できる技術や製品やサービスの開発が終わり、テストマーケティングを行う前後で企業が提携をすることができれば、双方にメリットが出る可能性がある。
事業会社は事業開発が効率的に進み、ベンチャーは不足する資源を獲得すると同時に、将来の販売網を一部確保するなどが見えてくる。場合によっては、1年分程度の運転資金を獲得して、じっくりと事業化に専念できるようになる。
が、このような取組を事業会社が取り組んだとしても、1社、2社程度は良いが10社から20社くらい同時並行して進めるとなるとかなり苦労する。そこで、提携や協業を行いながら出資を続けるCVCの存在が非常見魅力的に見えてくる。CVCは、LP1社に対してGP1社の1対1で運営する。そのためGPは事業会社の投資目的を実現するベンチャー企業をリストアップの段階から一緒に協議して進め、ミドルリストの絞り込みを行う。
例えば、30億円規模のCVCであれば、1億から数億の投資を1年で3本程度行いはじめの5年で投資を終える。その中で、提携で終わり投資をしないベンチャーもあるし、出資提携を行いながら事業開発の協業を行うベンチャーもある。複数のベンチャーを毎月投資後もフォローをしながら事業シナジーと財務リターンの両方を獲得するようにGPが細かくベンチャー企業と行動をともにするのだ。
そう、一定の金額予算を確保して事業シナジーを生みながらオープンイノベーションを実施するために、CVCの活用は非常に合理的かつ魅力的なのだ。
(過去の記事)
過去の「新規事業の旅」はこちらをクリックして参照ください。
(著書の購入)
「コンサルの思考技術」
「実践『ジョブ理論』」
「M&A実務のプロセスとポイント」