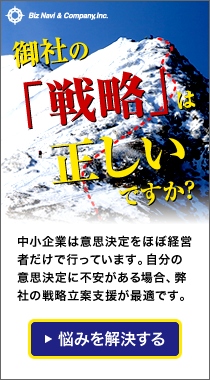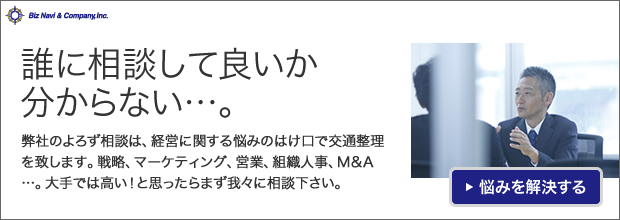早嶋です。
日経新聞の2045を探して、の特注が面白い。2045年はAIにおいて技術的特異点を迎えるとされる。いわゆるシンギュラリティ。人工知能が人間の能力を超える年がやがてくる。それが2045年という予測だ。
今回の記事では米国の大手法律事務所の事例が掲載されている。裁判における資料や証拠の整理をAIを使ってロボットが担っているという。米国は裁判が非常に重要で、したがって弁護士は一定の地位と名誉を獲得していた。が、過去の仕事の中で証拠や判例あつめに要していた時間を人工知能が行うことで時間請求の概念が崩れつつある。裁判にかかわる半数以上の仕事が資料整理だったからだ。それをロボットがこなすとなると請求の仕方が変わるのだ。
特集に出ていた法律事務所は、AIを上手く活用して裁判を進め、上級職になるための要件定義の1つにロボットを使いこなすことがあるという。世の中はやはり変わっている。
別の事例では人事の仕事をAIが肩代わりする事例だ。企業の規模が大きいにも関わらず、人事部の仕事を少人数で行う企業は多い。そこにAIを導入して仕事を効率化するという取り組み。が、ここには若干の盲点もあるかもしれない。それは感情が無いという点だ。AIは客観的な事実に基き学習を繰り返していくためその評価は極めて正当。裏を返せばドライな、感情が全く無い冷徹な判断が下されていく可能性があるのだ。
人間は、感情の生き物であって合理的に生きていない。そこに、完全に感情を抜いたところでの意思決定を行うと、組織の判断や戦略にどのような影響をあたえるのか。この取り組みに対しての症例や事例はあまりにも少なく、始まったばかりだから今後の動きを注視しなければならない。