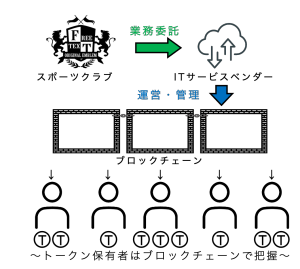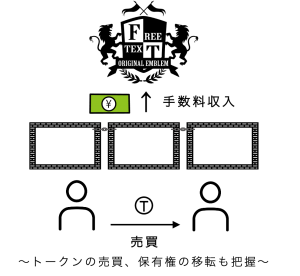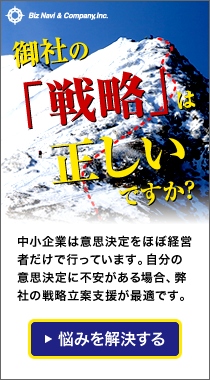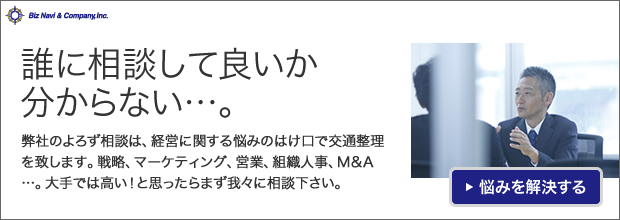早嶋です。
2016年6月23日の国民投票におけるEU離脱の選択から4年以上の歳月をかけて、離脱協定に沿って2020年1月31日にEUを離脱しました。そして去年1年間に英国とEU間の協定や取り決め毎に対して交渉が行われました。昨年の12月24日に英国とEU間の通称協力協定に合意。2021年1月1日からその協定の暫定適用が開始されました。
英国とEU、いや欧州大陸は歴史を辿っていくと元々が違うんだと思います。なんというか少し島国である影響もあり、個人主義でどこか引いた感じを受けます。なんとなく壁を作る感じはどことなく日本的な雰囲気もします。米国を引き合いに出すと怒られるかもしれませんが英語の表現も米国と違ってストレートではありません。我々日本人と同じで根底は島国根性があるのでしょう。
欧州大陸と英国はドーバー海峡によって隔たりがあります。この海峡は難所で、過去何度も欧州大陸から英国に攻め込む国がありましたがことごとく失敗。まさにドーバー海峡は英国にとっての守護神なのです。そしてそのお陰で英国は大航海時代の後半より力をつけてきました。ポルトガルやスペインが植民地政策を行っても、欧州が戦場になれば艦隊を自国に呼び戻す必要がありました。戦力が不足するからです。しかし英国はドーバー海峡があったため欧州での争いがあっても英国に攻め入る国が結果的に少なかったのです。そのため欧州が戦いに明け暮れていた隙きを狙って植民地を増やすという行動を過去繰り返しています。また、英国は直接自分の手を動かさず、戦略的にパートナーを誰かと組み、他人の褌で相撲を取ることを得意としていました。
本稿では16世紀から17世紀、18世紀から19世紀、20世紀と順を追って英国の歴史と欧州の動きを見ていきます。事実関係はWikipediaを中心に調べていますが、ところどころ早嶋の解釈も入っています。事実とは違う分はご容赦下さい。
(16世紀から17世紀)
16世紀。日本は戦国時代から江戸の初期でしたが世界ではスペインがぶいぶい言わせていました。時の権力者、フェリペ2世はスペイン帝国の最盛期に君臨した王です。その治世は欧州、中南米、フィリピンに及ぶ大帝国を支配しており、地中海の覇権を巡りオスマン帝国をも退けて勢力を拡大します。そしてポルトガルも手に入れイベリア半島を統一し同時にポルトガルが有していた植民地も継承します。その繁栄は「太陽の沈まない国」として形容されるほどで、強みの無敵艦隊を率いて海も制していました。
そんなフェリペ2世はカトリックによる国家統合を理想に掲げます。一方当時のオランダはスペインの飛び地でした。オランダは宗教改革を行い新教カルヴァン派を国教として奉じる国になっていました。そのためカトリックに対する誹謗中傷がじわじわ始まり、やがてスペインの逆鱗に触れ結果的にスペインからフルボッコにされたのです。
その頃英国は、スペイン、オランダ、ポルトガルの交易船などを襲う海賊に支援をし、海賊行為によって得た金銭でひそかに富みを得ていました。更に、オランダに肩入れをすることでスペインの虚を突くことができると企んだのでしょう。また宗教の見地からも英国はカトリックを止めていて女王陛下を英国国教会のトップとした背景もあり、スペインに対して何か感じることがあったのかも知れません。
このような積み重なりがありフェリペ2世は英国(イングランド)に無敵艦隊を送り込むことを決めました。ロンドンに上陸してエリザベス女王を捉えて宗教裁判を起こす作戦でした。しかしスペインは英国に負けてしまうのです。英国はドーバー海峡を熟知しており無敵艦隊を海峡の狭いところにおびき寄せ圧勝しました。1588年、アルマダの海戦です。英国艦隊に敗北したスペイン無敵艦隊はスコットランドとアイルランドを迂回して帰国を目指しましたが運悪く悪天候により更に被害を蒙ります。結果約130隻あった艦隊が本国に帰国出来たのは半数の67隻だったと言われます。
スペインが衰えると次に台頭した欧州の国はフランスでした。この頃のフランスを率いたのはナポレオンです。彼はフランス革命の混乱を収拾し軍事独裁政権を樹立しました。フランス革命が起きた当時、周辺国も王国だったためフランス革命の動きが自分たちの国にも飛び火して革命と同じような動きになったら困ると誰もが思っていたことでしょう。そこに英国が乗っかって、一緒にフランスをやっつけようぜ!となったのです。
しかしナポレオンは包囲網を突破し、西はスペインから東はドイツ、そしてロシアまでをも支配する勢力を持ったのです。フランスはスペインに変わり欧州広域を統一する存在になったのです。もちろん英国は黙っていません。フランスにしかけます、1805年、トラファルガー海戦です。ナポレオン戦争における最大の海戦とされ、英国はこの海戦の勝利によりナポレオン一世の英国本土上陸の野望を阻止しました。ロンドンにあるトラファルガー広場はこの海戦から名前を得ており、広場にはネルソン提督の銅像があるのもそのためです。
ナポレオンはこの戦いの腹いせに英国経済封鎖を試みます。フランスの同盟国に対して英国との貿易を止めさせたのです。しかし英国に農産物を貿易していた国々は穀物が売れなくなり困り果てます。この影響により時のロシアでは大規模な反乱が起こりました。そしてこれが仇となりナポレオン帝国は徐々に崩壊へと向かっていったのです。皮肉なことに自分が蒔いた種によって終焉を迎えます。
決定打は1815年御ワーテルローの戦いです。この戦いでフランスは英国や当時のドイツとの同盟軍に大敗して、ナポレオンは南大西洋の孤島セントヘレナへ島送りされ、1821年にその生を終えました。英国は1840年にナポレオンの遺体をパリに返すことを認め、今でもその遺体はルイ14世が建てた廃兵院のドームに安置されています。
(18世紀から19世紀)
18世紀。農業生産の飛躍的な向上を成し遂げた農業革命に続き、世界初の工業化を達成した産業革命が英国ではじまります。英国が自分たちの生産能力を向上させた背景は植民地政策と奴隷貿易の影響が大きかったと思います。当時の英国は欧州の国々が争っている間にいろいろな国々を植民地にしていきました。ドーバー海峡のおかげで欧州の国々が英国に攻め入ることが難しく、余った戦力を世界の植民地にむけることができたのです。結果、アフリカ、中東、インド、マレー半島、オーストラリア、ニュージランドを次々に植民地にしていきました。
植民地は関税なしに英国で生産した商品を売る市場でしたので、作れば作るほど売れる。そのため生産性を飛躍的に向上させるインセンティブがあったのです。英国は当時、世界の工場と称されたのも有名ですね。英国に取っては植民地政策こそが繁栄の鍵だったのです。
そんな英国の驚異はロシアでした。ロシアの多くは氷に覆われているため常に南下政策を考えます。地中海、中東、アジアと貪欲に攻め込むロシア。当然、英国としては欧州大陸がロシアの手に入ることを恐れていたので、植民地に向けていた海軍の軍事資源をロシアとの戦いに向け始めます。直接的に戦いを仕向けない英国が相棒に選んだのはフランスでした。
1853年、ロシアは南下政策を積極化させてオスマン帝国に宣戦。英国とフランスはオスマン帝国を支援して戦争がはじまります。クリミア戦争です。結果、ロシアは敗北してパリ条約で講話、オスマン帝国の領土は保全されロシアのバルカン方面での南下は一旦抑制されました。
ロシアはインドにも向かいます。ロシアは既にイラン進出にて戦争を起こし、アフガニスタン方面にも勢力を伸ばそうとしていました。英国にとってインド植民地の権益を防衛する大義があったので英国はアフガニスタンに侵略してアフガン王国の制圧を目指しました。これがアフガン戦争です。
ロシアは中国にも南下政策を仕向けます。ロシアとしても不凍港を欲していたのが理由です。当時ロシアは上述したバルカン半島での南下政策を断念していたので進出の矛先を極東地域に向けることにしました。日本は近代国家の建設を急ぐとともにロシアに対しての安全保障上の理由から朝鮮半島を自国の勢力下に置こうと考えていました。朝鮮を属国としていた清との戦い(日清戦争)に勝利した日本ですが中国への進出を目論むロシアが邪魔だったのです。ロシアは露清密約を結び満州への進出を推し進めていました。そして英国はこの関係を観察しており日本と手を組むことで、結果的に日本がロシアと戦うように導いたのです。日露戦争です。
当時のこの戦いはグレート・ゲームと呼ばれました。中央アジアの覇権をめぐる英国とロシアの敵対関係や戦略的な抗争を指す言葉で両国の情報戦をチェスになぞらえてつけられました。グレート・ゲームは20世紀の冷戦構造と全く同じで典型的なランドパワーのロシアに対してシーパワーの英国は直接ロシアに攻め込むことなく、適宜同盟国と一緒になり間接的にロシアを封じ込めました。クリミア戦争、アフガン戦争、日露戦争。結果的にロシアは疲れはて混乱状態に陥ります。結果、萎縮したロシアが選択した1907年の英露協商で英国とロシアの互いの争いは終了しました。
(20世紀)
20世紀。新たな敵国が出現します。ドイツです。ドイツはロシアに変わる新たなランドパワーとして台頭し2つの世界大戦を引き起こします。当然英国は2回とも連合軍をつくり叩きのめしました。第二次世界大戦の時はヒトラーが群衆を率い欧州をほぼ占領します。その範囲はフランス、オランダ、ベルギー、デンマーク、ノルウェー、東ヨーロッパ、モスクワまでと、とても広域に攻め込みました。ドイツは陸軍主体の戦いが得意だったのでドーバー海峡を超えて英国に攻め込むことは苦戦していました。
それでもドイツは空軍を使って英国に攻め込みます。ロンドンは無差別空爆を受けますが、時の首相のチャーチルは絶対に屈しない姿勢を示します。ドイツは北フランスから飛行機を飛ばしたため、英国の北部まで攻め込むことができず、逆に英国は北部からダイレクトにドイツに飛ばした飛行機によってドイツを叩きのめすことができました。当時の飛行機は今ほど距離を稼ぐことができず、空の戦いでもドーバー海峡が英国に見方したのです。
ヒトラーは英国を諦め、代わりにロシアを攻め込みます。そこで英国はロシアと手を組みドイツを攻撃しようと考えました。この頃、あろうことか日本が勘違いして米国に戦争をしかけます。当時の米国は欧州での戦争をためらっていましたが日本が宣戦したことによって目覚めてしまったのです。そして英国、チャーチルすかさず米国を見方につけて、陰で日本と米国の戦争を操ることを目論んだのでしょう。
結局、ナチス・ドイツは崩壊して英国と手を組んだロシアが再び東欧とドイツに勢力を伸ばしていきます。ドイツは東側がロシア、西側を英国と米国が分断することになりました。米国はNATOを結成して独立した加盟国が外部からの攻撃に対応して相互防衛に合意することで集団防衛システムを構成します。対するロシアはワルシャワ条約を結びこの勢力に対抗しました。
当時の英国は完全に米国におんぶにだっこで本来は当時の大英帝国を復活したかったでしょうが戦疲れがあったのでしょう。その間に植民地が次々に独立していったのです。皮肉なことに、植民地の独立運動に火をつけたのは日本でした。日本が取った大東亜共栄圏の思想がフランス領や英国領だった国々を奮い立たせ、両国の植民地だった国々は次々に独立していきました。ロシアが東ヨーロッパの共産化を進めるなか、英国は悔しい思いをしたことでしょう。単独では何もできないと判断して米国と手を組みました。元々は同じ英語圏で、その昔は英国の植民地だった米国。なんとなく英国は下にみていましたが米国の助けなしに頑張れなかったのです。
そんな折、1956年にエジプトのナセル大統領がアスワン・ハイ・ダムの建設費財源を得るためにスエズ運河の国有化を発表しました。スエズ運河は1869年に営業開始、1875年に英国が買収し株主となっています。そのため株主である英国やフランスに多大なる富をもたらしていました。エジプト革命を成功させたナセル大統領は当初、アスワン・ハイ・ダムの費用援助を米国に求めましたがナセル大統領はロシア寄りの姿勢を取っていたため米国に断られたのです。結果、スエズ運河の国有化を思い付いたのでしょう。これがスエズ戦争です。
当初、英国は優位な展開をリードしていましたが、ロシアがエジプトを支援するという名目で軍事演習を開始します。本来ならば米国が手助けしても良かったのですが米国は助けませんでした。というのもロシアでスターリンが死去し米国とロシアの関係が良好になりつつあったからです。当時の米国大統領、アイゼンハワーもその関係を再び冷えた状況にしたくなかったのです。英国としてはNATOのメンバーなのに米国に助けてもらえない状況に苛立ちを覚えたと思います。
産業革命後、植民地あってこその英国。これはフランスも同じでした。自国で生産した製品が関税なしに自由に売れる市場が植民地だったので、経済を豊かにすることが可能でした。そのため英国もフランスも同じような仕組みを再び作れないかと考えました。そしてこれらが統一欧州の発想につながったのです。欧州全体を市場と捉えて自国の経済を発展させようと企んだのです。
フランスはドイツに対して二度と戦いたくないという思惑もあったと思います。歴史の中でフランスは何度もドイツに攻め込まれた嫌な記憶がありました。ドイツの怖さを十分に知っているのです。そのため英国よりも統一欧州に向けて先に動いたのはフランスでした。西ドイツとの和解というインセンティブが英国よりも高く行動が早かったのです。
欧州経済共同体(EEC)の当初の加盟国はフランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ベルギーでした。英国は、これに対抗してEEC非加盟の英国、オーストリア、スウェーデン、スイス、デンマーク、ノルウェー、ポルトガルとともに欧州自由貿易連合(EFTA)を結成します。政治統合を目標とせずに、域内関税撤廃、EECと異なり共通関税の設定をしない連合体です。
どちらの組織も徐々に加盟国を増やしていきましたが、やはりフランスとドイツが手を組んだら最強でした。EFTAもスペイン、ポルトガル、スイス、北欧チームを集めて運営していきましたが上手くいかず、結果英国はプライドを捨ててフランスに仲間に入れてもらうこととなったのです。英国としては自国の経済状況の悪化には背に腹は変えられない常態だったのでしょう。工場がバタバタ倒産して、労働者がデモりまくり、リストラ反対の嵐。そして賃上げを望む労働者とストライキしまくる労働者でとにかく大混乱だったのです。国が荒れて英国病と揶揄された時代、英国としても不本意な時代だったと思います。
1973年、英国とデンマークが欧州共同体(EC)加盟に伴いEFTAを脱退。1986年、ポルトガルがEC加盟に伴いEFTAから脱退。その後アイルランド、ギリシャ、スペインも加盟して1986年には12カ国に拡大します。そして世の中は冷戦が終わり、東ドイツが民主化運動を起こしベルリンの壁が崩壊。ドイツという大国が再び誕生しました。本能的にドイツを恐れているフランスはドイツ復活を恐れたのでしょう。ドイツを取り込んで欧州全体を一つとすれば問題ないと考えました。今の欧州連合(EU)の始まりです。
ECは市場統合が目的でしたが、EUは経済分野に関して超国家的性格を持つ欧州共同体の枠組みが目的でした。共通の外交、安全保障政策、司法、内務協力という加盟国政府間の協力は画期的です。更に通貨の統合が進められ1998年に欧州中央銀行が発足、翌年から単一通貨ユーロが導入されました。
(ドイツの巧みな活動)
フランスはドイツを恐れてEUの制度を成立させましたが流石はドイツ。EUの枠組みを正当に活用して自国に利潤をもたらそうと考えます。まずは通過です。通貨がバラバラであれば富を得ている国、つまり利益を得ている国の通貨の価値が上昇します。そのため元来から米国や日本やスイスの通貨価値は高値をつけていました。
ドイツは元々ものづくりでも優等生でドイツマルクの価値も高かい状況でした。当然、他国と貿易をする際はドイツマルクの価値が上がっていたのでドイツ製品は他国に取って割高な商品になっていました。特にドイツ御三家のベンツ、BMW、アウディなどはドイツマルクの価値上昇も加わって他の車と比較しても超高級車として取引されました。ところがEUがユーロに統一することでマルクがなくなります。ユーロは仮想国家でドイツが優秀でも他の加盟国の信用はまだまだ高いとは言えません。そのためユーロの価値は相対的に上がりにく構造になっていました。
その結果、ドイツはドイツ製品をユーロで売ることで、加盟国の中では割安に見せることに成功しました。日本が円高で苦しんでいる時にもドイツはユーロ安でボロ儲けすることが出来たのでした。ドイツを恐れたEUの制度が逆にドイツを成長させるコントロールレバーになったのです。これはフランスにとっても予想外だったと思います。
ちなみにユーロにも中央銀行があり、所在地はドイツのフランクフルトです。各加盟国が出資して、その出資額に応じて発言権が強くなります。ドイツが最も出資額が多く実質ユーロはドイツが仕切っています。英国からするとここも不愉快だったことでしょうね。ただ英国はユーロの導入をしませんでした。自国通貨を手放せば通貨発行の権利を失います。多くの国々は景気が悪い時は自国通貨を刷りまくってごまかしています。もしユーロを使用するとなるといちいちドイツの許可が必要なり英国にとって不都合極まりなかったのでしょう。。
ドイツのメルケルは積極的に移民を受け入れる政策をとりました。表面的には移民に感情移入をし可愛そうだとしていましたが、経済的には移民の労働力を欲していました。当然、ドイツ国内の産業を下支えするためです。ただドイツも高齢化になりつつあり社会保障等の負担は日々大きくなります。そこでドイツは考えました。EU皆で移民を受け入れて対応しましょうと。そしてもし受け入れたくないならばその分お金を出しませんかと。
当然、移民からすると仕事があって賃金があって保障が充実するエリアにいきたいのでドイツや英国が専らいいねとなるのは自然です。SNSでこっちはこんな条件だぞ!とか言ってみんなが英国を目指し始めるのです。英国民からするとこれまで自分たちが将来のために払ってきたお金を、なんで移民に分配しなきゃいけないんだ!となって騒ぎ始めたのです。その時の首相がキャメロンで、メルケルとの交渉材料にと国民投票でEUに残留するか出ていくかを決めようと考えたのです。当時のキャメロンの思惑では五分が6対4くらいで残留が勝って、その内容をメルケルに突きつけて、あなたの要求は聞きませんよ!というシナリオを考えていたのでしょうが、ご承知の通り出ていく!という流れになっちゃったのです。そして国民の意思ということで英国政府は当然に無視できなくなります。その結果、離脱しますねとなったのです。
当時、その程度の理由で国民投票を行ったものですから、実際に英国がEUを出たらどうなるかなどのシミュレーションは殆ど行なわれていなく、出ることが決まった後に、マーケットはどうするかとか、関税がまたもどるぞとか様々な契約を見直す必要がでてくる、という感じで色々と不都合な事実がじゃかじゃか後出しジャンケンのようにでてきたのです。しかし後の祭りです。
その頃ドイツは英国は実は残りたいだろうと踏んでいました。そのことを逆手にとって英国から条件を引き出そうとあーだ、こーだ、様々な条件を英国に突きつけ、時には内政干渉と取れるようなこともしていました。なんとなくグチグチしていて英国からは嫌だなーとなっていたのでしょうね。結果、英国の保守党政権内でも離脱派と残留派が対立、EUとの条件闘争ももちろん決裂しました。最終的には保守党の離脱派、ボリス・ジョンソンが総選挙で圧勝してしまい正式離脱を表明したのです。
(ボリス・ジョンソン)
ボリス・ジョンソンは2015年の下院議員の前はロンドン市長を2期8年務めています。ニューヨーク生まれで米国と英国の二重国籍を持っており、前メイ政権の外相に起用された時点で米国籍を捨てています。ボリス・ジョンソンとキャメロンは名門パブリックスクールのイートン校からの盟友でしたがブレグジット国民投票では離脱派と残留派で戦うことになりました。ただ、両人ともEUから距離を置く伝統的な保守党のリーダーだったので本気で戦ったかどうかは不明です。
本稿でも示した英国病と形容された1970年代の長期経済低迷期、ボリス・ジョンソンとキャメロンはマーガレット・サッチャーの言動に影響を受けています。当時のサッチャーのスピーチに、次のような記録があります。「ソ連のように中央から仕切る国が今は権力分散が大事だと言っている。それなのに欧州共同体は逆行して権力を中央につけようとしている。フランスはフランスとして、スペインはスペインとして、英国は英国として独自の文化や習慣やアイデンティティを持ってるから強くなるんだ。」と。
また、二人はチャーチルの思想にも強く影響を受けていると言われています。第二次世界大戦前チャーチルのメッセージです。「英国は欧州と連携しているがその一員ではない。欧州とともにあるが、欧州は英国ではない。我々は欧州に関心を持ち、結合しているが欧州に組み込まれているわけではない。」と。
そしてボリス・ジョンソンはロンドン市長の時に「EUの目的は本質的にはアドルフ・ヒトラーと同じだ」とし、「英国はEUという超国家に取り込まれるべきではない、ユーロは生産力あるドイツに絶対的なアドバンテージを与え、その他ユーロ圏の国々はドイツに絶対勝てない仕組みになっている。」とユーロを批判していました。ボリス・ジョンソンとしてはようやく自分の考えを体現する活動が始まったのでてワクワクしているのでしょう。
(英国の分断)
国民投票の結果は興味深いものがあります。地域的に見て残留か独立かが明確なのです。スコットランドなど北部エリアは残留派が多く、イングランドは独立派が多いのです。スコットランドのウィスキーは欧州で売れていましたが関税がかかると高くて売れなくなります。英国のEU離脱によってスコットランドは英国から離脱してEUに戻る意向を示しています。
2020年12月末、ボリス・ジョンソンが示した挨拶の中で「手にした自由を最大限に活用するかは私たち次第」と強調し、「世界中と貿易協定を結ぶことができる」と、EU圏外の各国と独自に経済関係を強めていく姿勢をしめしていた時、スコットランドのスタージョン自治政府首相は完全離脱後から、「スコットランドは間もなく(EUに)戻る」「私たち自身が私たちの未来を担う時だ」と相次いでツイッターに投稿しています。
英国のEU離脱は北アイルランドにも大きく影響します。北アイルランドは元々はアイルランドで全体の25%程度が英国からの移民です、アイルランドが独立する際に英国の一部になっています。英国系はプロテスタントでアイルランド系はカトリックと宗教的な対立も揉め事の背景に隠れています。これらの解決策の1つとして国境を無くすことがあり平和が取り戻されました。しかし今回のEU離脱によって、再び国境が生まれると再び揉め事の原因になりかねないのです。
今後、ジョンソン政権は欧州以外にマーケットを求める動きを加速します。保守党はマーケットとして中国もみていましたが香港問題やウィルス問題で険悪になっています。米国に関しては協定を結んで関税をゼロの方向に調整しています。そしてTPP。太平洋周辺国の関税無しの協定です。見渡せばかつては英国の植民地だったエリアで、英国との相性も良く日本にとっても実質的な日英の貿易協定につながっていきます。
EUは中国と接近し、英国は日本に近づく。再びランドパワーとシーパワーの戦いが始まるのでしょうか。
参照:
Wikiペディア、日経新聞、ロイター通信、各国外務省Webサイト