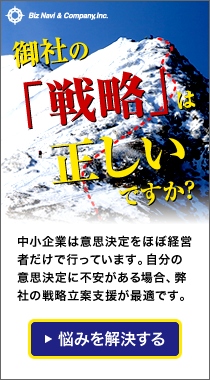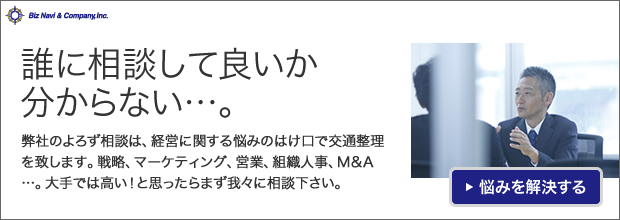早嶋です。
(キャンバスに自由にかけない)
小さい頃、自由に絵を描きなさいと言われた時に、「目の前の果物を擬人化して、その果物が食べられる瞬間に、人に掴まれて皮をむかれる悲壮な姿をイメージして」絵を描いたことがあります。少なくともそのような情景を浮かべていました。表現力は無かったものの、出来上がった絵は誰も理解できない絵だったようですが、当時の早嶋少年は大満足でした。
当時のお題は、果物の静物画。家からもってきた果物をみんなで描く授業でした。でも先生が並べる配置は、教科書通り、なにも面白味が無く感じました。しかし先生は自由に好きなように描きなさいという。周囲は、完全に教科書通りの絵を描いて、私は自由に描くという言葉に引っ張られ過ぎて暴走したのでしょう。
自由に絵を描きなさいと言われ、筆が進む人は少なく、何かをお手本に絵を描いていくことで自分の作業を進めることに安心する人が世の中的には絶対数だと思います。既存の事業を与えられ、細分化さらたバリューチェーンを一生懸命に覚えて経験を積んで成果を出す。だれも新規に自由に事業を創造することなどしたくないと思うのです。ここに自由の本質があるのだと思います。
(プロテスタントの出現)
マルチンルター。若いころに経験した苦を抑えるためにアウグスチノ修道院に入り修道生活をはじめます。しかし修道に励めば励むほど彼の中で矛盾が生じていきます。半ば神に対しての絶望があったのだ、というより神を利用している一部の権力者の愚行に怒りを感じたのしょう。そんななかパウロの言葉が彼をあらたな方向にリードすることになります。
「神の儀は信仰に始まり信仰に至らせる」だ。
当時は一部の教皇が聖典の解釈を活用して、罪に対しては免罪符を購入することで救われるという慣行があった。まさに、お金によって好き放題する一部の富豪や権力者の暴挙が目に浮かびます。当然、富の分配を受けない多くの一般市民は悶々とした日々を過ごしたことでしょう。ルターはそのような取組を一切否定し、信仰の究極的な権威は聖書であり、聖書と共に教会の権威を持つカトリックの思想に対立したのです。
ルターが唱える考えは、従来の信徒の信仰生活に大きなイノベーションをもたらしたことでしょう。洗礼とミサのみを残し、教会主導の不合理な活動は廃止、典礼はラテン語からドイツ語に翻訳され説教中心の内容になりました。修道士や聖職者の身分をフラットにして、自らも妻帯に踏み切ります。そして一般初等義務教育の概念を導入して近代の教育制度を打ち立てたのです
。
欧州におけるルターの宗教革命は、単にカトリックとプロテスタントの対立のみならず、政治、経済、国家、階級、教育、思想、文化などに複雑にからみ当時の世の中の変革に大きく寄与しています。ルターの「人は悪」、そのために「自我を消し、神に服従する考えや、ひたすら勤労することで神に服従する思想」は、やがて近代資本主義のベースを作ったと思います。
(ファシズムの台頭)
藤沢道郎著「ファシズムの誕生」には、1920年前後のイタリア政治や社会状況をドキュメンタリー調で描写されています。第一次世界大戦から主人公のムッソリーニを中心に三島由紀夫も傾倒したマルクス主義の思想家であるグラシム、長らく首相を務めたジョリティなど当時を代表する登場人物の考えを垣間見ることができます。ファシズムそのものは独裁の一種とされるみたいですが、その範囲は多数の議論がされています。ひとつの分かりやすい考えは、自由を反する思想です。
ユニークなのは、自由を求めて自由になったとたんに、なんだか息苦しくなっていく。だからと言って完全に共産的な取組も嫌だし、保守的な動きも嫌だ。そこで何らかのリードしている人の下に従属した方が気持ちが楽になる。というような考えがあったのでしょう。
フロム著の「自由からの逃走」はまさに自由の代償について論じた本です。封建社会の中にいる人々は、役割があり、その役割を全うする中で自由があった。しかし世の中の革命児の出現とともに毎度その制度が崩壊することで、本来籠の中の鳥としての自由が無くなり、鳥かごの外に出た瞬間に自分を律することができなくて混沌としてしまう。歴史はこのサイクルを繰り返しているのでしょう。
フロムの主張では、本来の自由の中に取り残された多くの人間の行動は次の3つに行きつくと言います。そのキーワードは権威、破壊、画一です。
(自由の代償)
権威は2つの方向性があります。完全に自由になれば、その自分の自由さに対して不安が生じます。その結果、社会的欲求が強くなり何かの組織に属したくなります。ファシズムの台頭が、当時ピシャリはまった理由は、個人が自由に開放された結果、今度は一気に不安になった背景があったと思います。
一方で、ある程度自分の主張ができる人は、周囲からの承認欲求が強くなり、自分の権威を使って組織化したくなります。どちらの方向性も人間が求める権威に対しての志向でそもそも人間は力以外のなにかにすがりたくなるのでしょう。
動物の世界では、この権威はおそらく力そのものだったと思います。近くの動物園の猿山は、「権威=力」です。リーダーは常に力を示し、組織を統率します。そのため力による序列があり上はNo1 から力の順番ができているそうです。ただ、あまり記憶が良くなく、時々No8とNo9が勘違いして喧嘩をして力関係を確かめるなどの行動が観察できる層です。また、当然No1は老いなど何かしらの理由でNo2に負けることがあります。人間の世界以上に、力で負けたリーダーの末路は悲惨だそうです。
人間は外部からの刺激を自分のアタマで解釈して動くことを覚えた結果、力以外の何かで自分達の強さを示すことができるようになりました。その結果、力に加えた権力が動物界よりもより発展していくことになったと思います。
2つ目は破壊です。自由に生きているはずが、なんだか不安になってしまう。ふと自分よりも自由に生き、周囲で活躍する人を見た瞬間から自分の自由に疑問を持ち、葛藤が始まり、嫉妬を抱くようになります。その時の人間の対応が破壊です。周りを悪だと認識した人間は、何らかの方法でその人を潰してしまう、或は危害を加えなくとも、その人の存在がなくなって欲しいと願います。この直接の行動や思想を持つことそのものが破壊の象徴です。逆に、自分を悪だと認識した人間は、自分の存在をこの世から消してしまいたい、自分がい無くなれば良いと考えてしまいます。やはりこの行動や同様に発想すること自体もやはり破壊の始まりです。
フロムの最後の主張は画一です。自分の考えを消し、ただただ周囲の考えに交じり、あたかも同じ自分を楽しむのです。周囲と自分が同じだと認識することで、周囲との相対的な比較が不要になり自分の均衡を保とうとするのでしょう。
思春期に自分を表現する若者が2種類いたとしたら、髪の毛を真っ赤に染めて突っ張るヤンキーと、流行を追いかけ朱にそまるマジョリティです。どちらも罪は無く、自由を手に入れたいが本来の欲求が結果的に苦しくなり、大多数の人間が画一に染まることで安堵を感じていくのです。若者を中心に同じような格好や言葉やスタイルを好む昨今、完全に自由になることへの恐れを抱いているとも考えられるのです。
(八百万の神にっぽん)
フロムが著書を書いた時期は1966年。今のスマフォ片手にコピペによってすべてが構築できる社会は、当時からすると画一世界の集大成でしょうね。デジタル化はモノゴトを完全にコピーし同じにすることですから、違いがでない。そのためにグローバル化により、世界を完全に一つやいくつかのパターンで統合できると考える権威保持者が出てきたのです。中世は王族や侍大将がエリアの統合を目指し、近年は企業が世界制覇を目指します。
すべてを統一化できるという発想自体、すべてのモノを均一化することができるという究極の過ちのような気がします。権威をかざせば、その権威の中で、昔の封建的な制度が復活して、その枠組の中で人々は安堵して生活すると。
考えてみると、この究極のポジションをとりがちな思想が絶対伸の存在か、多神教的な発想かにつながるのではと思います。今回の議論のスタートは宗教革命です。そしてその革命は一神教をベースに勃発しています。一方で日本古来の神はいたるところにあり唯一無二と考えません。西洋の思想は偶像崇拝の有無はあるにせよ、基本的に神はひとつです。この一神教と多神教の考えそのものに、思想としての根底に自由を与えるか否かが見え隠れしていないかと思います。
フロムの主張はその意味でも非常に興味深いです。自由からの逃走の果てには何があるかと言えば、「自発的な活動と世の中を結び付ける行為、そして他者に与えること」とフロムは表現していました。
自由にいきましょう。自由に表現しましょう。自由に作文して下さい。自由に創造してみて。きっと多くの人は、「自由」という何も無い空間に自分を置くことを創造すると急に怖くなり、結果的に何らかの制約条件の基で動くことに安心を求めるのでしょう。一方で、一定数はその自由が好きで何も縛られない世界を築くことに喜びを持つ人間もいるのです。
きっと後者の人間は、ある意味、覚醒しており悟りを開いた状態か何らかの神経メカニズムがマジョリティと異なるかなのでしょう。ただ自然の中にいれば花鳥風月があり、すべての景色は異なり、毎日が移ろうことを知っている日本人は、画一に染まることなく足るを知り、権威を示すことなく、権威に依存することもなく。周囲を破壊することなく、自分を潰すことなく、ありのままの自分で行動し思考し生きることができるのかな。
だけど、それが出来ないと思っているから苦しいのでしょうね。